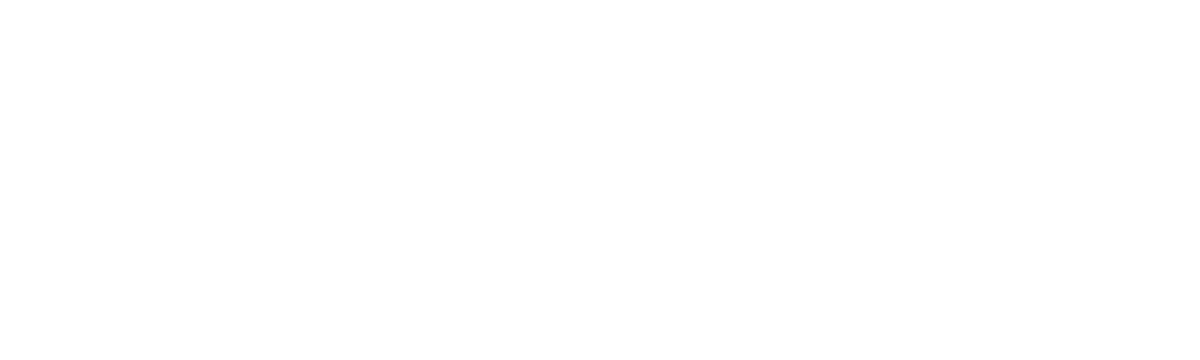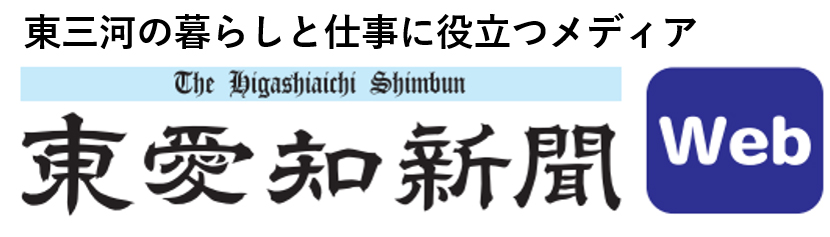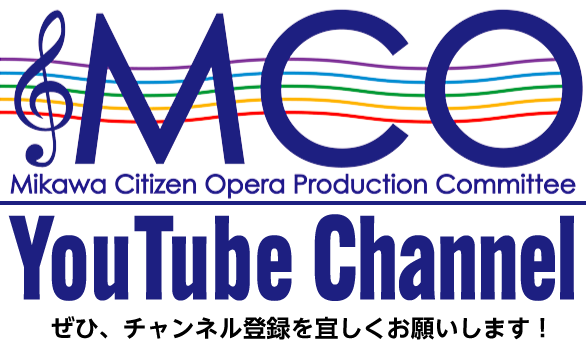Headline News
東愛知新聞にて新連載が始まりました
東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての連載⑤

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。
【連載】三河市民オペラの冒険〈5〉
三河市民オペラはどうすごいのか
(音楽評論家・河野典子)
三河市民オペラ(以下、「三河」)は数ある市民オペラでも特殊な存在で、それは「制作委員会」の働きに帰するところが大きい。
制作委員会のメンバーが地元企業経営者らに頭を下げて回って公演の資金をかき集め、チケットを売り、マイカーを出して出演者や関係者の送迎運転手もこなし、当日は「携帯電話のスイッチをお切りください」というプラカードを持って客席をくまなく歩き、公演中に高級ホテルのドアマンよろしく、扉の前に立ったまま舞台を見守る彼らの姿には、ワーグナーのオペラ「タンホイザー」の巡礼の合唱が聴こえくるような崇高さすら感じるのだ。普段オペラとは縁のない人たちがそれらを手弁当で務めているのである。「熱い感動を生み出す」というつかみどころも捉えどころもないようなことを目標として、いい歳をした(失礼)大人たちが一丸となっているところこそが「三河」が他の市民オペラと違う点だ。
新国立劇場をはじめとした公立の劇場、年に数回のオペラ公演を打ち続けることが求められる、いわゆるプロのオペラ団体は、毎月のように次の作品のキャスティング、準備、稽古そして公演を繰り返す。「三河」は数年に一度だからこそ、これだけのことができるのであって、そこを同列に語ることはできない。だが、東京や関西圏を中心に活躍する歌手たちが、こぞって「三河」の公演オーディションに、新幹線代を払ってまで集まってくるというのは、他の市民オペラではまず見られない現象である。出演者たちを触発するのは、制作委員会メンバーが醸し出す「やる気」と「本気」である。
成功を重ねれば重ねるほど、そこに期待と責任が生まれてくる。事前に出演を依頼する指揮者、演出家、数名の歌手たち以外については、公明正大なオーディションを行わねばならない。地元の合唱団やオーケストラ、舞台のみならず手を貸してくださる数多のスタッフの方々とも熱意を共有して活動しつづけること、国内外の他団体からノウハウを聞かれれば、それをつまびらかにしていくこともこれからもっと求められるだろう。それが、衰退しつつあることを否めない「日本におけるオペラの存続」に直結しているのが今の「三河」の立ち位置である。
「三河」はこれまで「魔笛」「カルメン」「トゥーランドット」「イル・トロヴァトーレ」「アンドレア・シェニエ」と公演を重ねてきたが、オペラというもののも魅力を地元のお客さまに知っていただき楽しんでいただくためという目的のもと、日本人歌手が歌うには重すぎるレパートリーに向かって舵を切ってきた。集客力という点で、大きなオペラ作品を採り上げることは大事な要素ではある。だが、重いものばかりが素晴らしいオペラというわけではない。歌舞伎でも「勧進帳」や「暫」のような様式美の時代物もあれば「髪結新三」や「廓文章」などの世話物があるように、どちらかがお好きな方もあれば、同じ役者さんがどう演じ分けられるかを楽しみに劇場にいらっしゃるお客さまもある。「風の谷のナウシカ」のような新作物に若い観客が押し寄せることもある。
オペラ関係者と「お客様をなめるな」と話すことがあるのだが、「難しいものはわからないだろう」「有名なものを掛けていれば安全だろう」という発想はとんだ筋違いだということを「三河」は「アンドレア・シェニエ」で証明して見せた。いわば通好みの「シェニエ」で普段オペラをご覧にならないお客さまを感動の渦に巻き込んだのである。
さてここからの「三河」が、演奏家の「一度は手掛けてみたい」という身勝手な都合に振り回されるのではなく、どんな自分たちの基準を持って、どこに向かっていこうとするのか。私はそれをとても楽しみに見ている。
◇
東京藝術大学卒業後7年間在伊。帰国後、執筆活動、歌手のサポート、録音プロデューサー、文化庁の審査員などを務める。著書に「イタリア・オペラ・ガイド」。
東愛知新聞にて新連載が始まりました
東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての連載④

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。
【連載】三河市民オペラの冒険〈4〉
唯一無二の魅力を確信した瞬間
(バリトン・上江隼人)
私が三河市民オペラに関わるようになったのは、2017年の「トロヴァトーレ」公演からです。市民団体がヴェルディの名作に挑戦すると聞き、「どこまでできるのか」と不安と期待が入り混じりました。しかし、その公演は大成功を収め、チケットは完売。さらに、三菱UFJ信託音楽賞を受賞するという快挙を成し遂げました。
以来、私は歌い手として関わり続けていますが、三河市民オペラの「本物の音楽は必ず伝わる」という信念に深く共感しています。通常、市民オペラは地元の音楽家を中心にキャスティングしますが、三河市民オペラは公開オーディションを実施し、純粋に音楽の力でアーティストを選ぶ。これは、目に見えない「音楽」という芸術を扱う上で、非常に勇気のいる決断です。
しかし、この姿勢があるからこそ、歌い手も期待に応えようとし、普段以上の力を発揮できます。それを実感したのが、この団体の舞台でした。オペラは、人と人が支え合いながら創り上げるもの。決して順風満帆にはいかず、さまざまな苦労もありますが、その先に生まれる舞台には、特別な力が宿ります。三河市民オペラの公演には、まさにそのエネルギーが満ちている。そう気づいたとき、この団体の唯一無二の魅力を確信しました。
オペラは生の芸術です。何が起こるかわからないし、すべてが完璧にいくとは限らない。それでも、お互いを信じ、本番に臨む。その瞬間を共有できる環境があることは、決して当たり前のことではありません。そして、時が経ち、新たに「アンドレア・シェニエ」の上演が決定。「非常に難易度の高い作品だけれど、三河市民オペラならきっと実現できる!」そうワクワクしたのを覚えています。この公演も完売し、第10回JASRAC音楽文化賞と令和5年度愛知県芸術文化選奨文化賞を受賞。オペラ界に新たな希望をもたらしました。
これから三河市民オペラがどのように進化していくのか、とても楽しみです。オペラは伝統と最新技術が融合しながら発展してきた総合芸術。過去の黄金時代をなぞるのではなく、現代の最先端を切り拓く。そんな挑戦を、三河市民オペラが率先して行ってくれることを期待しています。
例えば、有名メーカーやアーティストとのコラボ(衣装・舞台デザイン)▽海外の芸術家や音楽家との共演▽新たな演出(プロジェクションマッピング、海外配信)▽他の伝統芸能(歌舞伎や能)との融合―など、
こうした試みが、三河市民オペラならではの魅力になっていくのではないでしょうか。この素晴らしい団体が、これからどんな舞台を創り上げていくのか、心から楽しみにしています。そして、これからもその舞台に立ち続けられることを願っています。
◇
東京芸術大学大学院を首席で修了。2006年、ディマーロ国際声楽コンクール優勝。同年、ヴェルディ・フェスティバルで「トロヴァトーレ」に出演し、イタリアデビュー。その後、パルマ王立歌劇場やシチリア・ベッリーニ劇場など国内外の主要劇場で活躍。「リゴレット」「カヴァレリア・ルスティカーナ」などで主演し、高い評価を得る。近年では、藤原歌劇団「二人のフォスカリ」(2023年)、新国立劇場「ドン・パスクワーレ」(2024年)、藤原歌劇団「ファルスタッフ」(2025年)などに出演。受賞歴も豊富で、平成24年度五島記念文化賞オペラ新人賞、令和2年文化庁芸術祭新人賞を受賞。2021年にはデビューアルバム「ヴェルディアーノ」をリリース。NHKニューイヤーオペラコンサートにも連続出演。現在も藤原歌劇団正団員、日声協オペラアカデミー会員として活動を続けている。