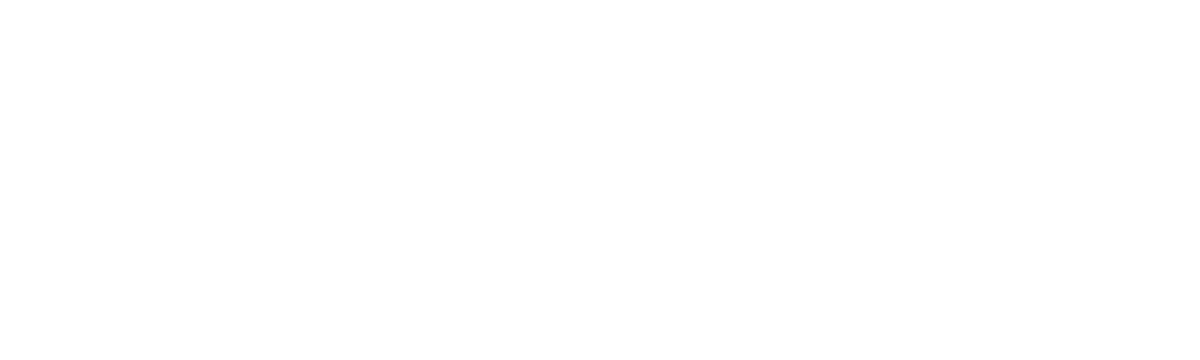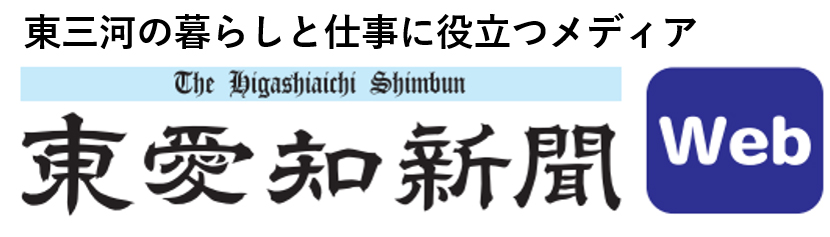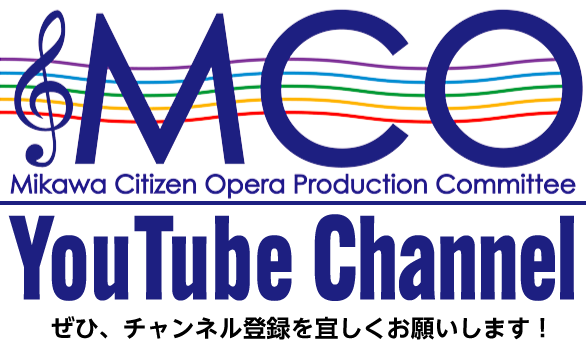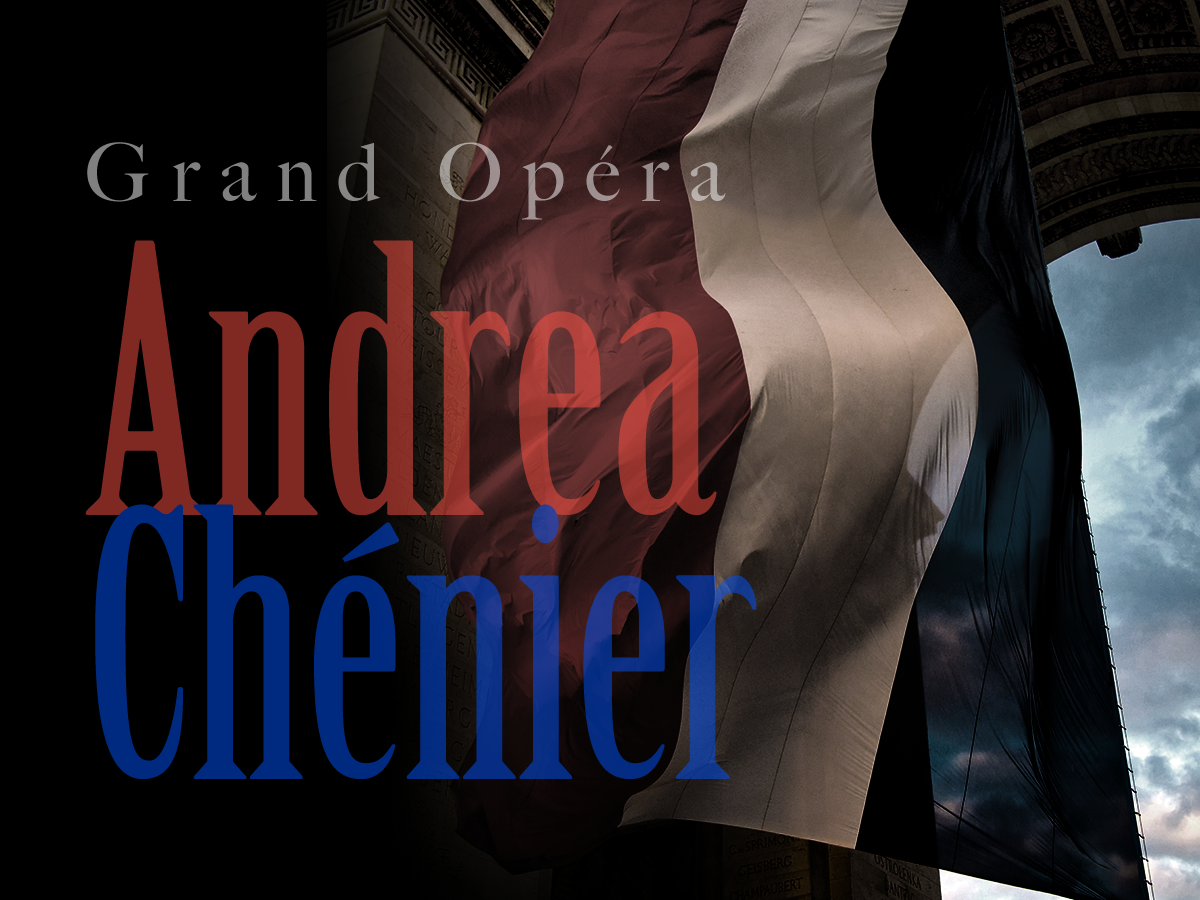Headline News
東愛知新聞にて新連載が始まりました
東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての連載⑥

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。
【連載】三河市民オペラの冒険〈6〉
挑戦し続ける姿勢が道ひらく
(ソプラノ・森谷真理)
私と三河市民オペラの出合いは、2017年「イル・トロヴァトーレ」のレオノーラ役でした。当時はまだ海外在住で、日本の市民オペラには初めての出演でした。
オーディションは公開形式で、多くの方が見守る中、驚きつつも課題曲を歌い帰宅したことを今でも鮮明に覚えています。その後、リサイタルやガラ・コンサートへの出演を重ね、23年には「アンドレア・シェニエ」でマッダレーナ役を務める機会をいただき、気づけば8年にわたるご縁となりました。
三河市民オペラ制作委員会の皆さんの「完売・満席を目指す!」という熱意、そして「チケット販売はこちらに任せて」という力強い言葉には心を打たれました。また、「満席でなければ次回公演はない」という潔さには、本当に驚き、感服しました。その覚悟こそが、三河市民オペラが多くの人々に愛され、支えられてきた理由の一つなのだと強く感じています。そして、関係者だけでなく、観客の皆さまも一体となって公演を成功へと導く。このような環境で歌わせていただけることは、私にとって大きな喜びであり、誇りでもあります。
三河市民のファンの皆様は盛大な拍手で演奏に応えてくださいました。そして、合唱団の皆さまは、初めて稽古をご一緒した日から温かく迎え入れてくださいました。また、愛知県近辺の演奏会にとどまらず、東北から九州まで全国各地のオペラ公演や演奏会へ足を運び、応援してくださいます。その熱意と愛情には、感謝の念が尽きません。
感動の形も、感動へ導く方法も、一つではありません。オペラは、さまざまな要素が融合する総合芸術です。その表現には無限の可能性があり、毎回異なる感動を生み出すことができます。三河市民オペラは、これまで多くの成功を重ね、素晴らしい実績を築いてこられました。しかし、もし次回があるのであれば、これまでの成功に安住することなく、常に新たな可能性を追求し、挑戦を重ねていってほしいと思います。そして、これからも観客に驚きと新たな感動を届けてくださることを願っています。その挑戦し続ける姿勢こそが、多くの観客を魅了する理由の一つであると確信しています。
三河市民オペラの活動は、単なる地域の文化活動にとどまらず、三河を拠点として生まれる熱い衝撃が日本全国へ、そして世界へと広がっていく可能性を秘めています。その未来を思い描きながら、これからも冒険を続け、観る者の心を揺さぶる感動を届けてくださることを期待しています。また、多様な音楽作品を新たな試みを通じてより多くの方々に届け、その多彩な魅力を発信し続けてくださることを心より願っております。
◇
武蔵野音楽大学、同大学院卒業後、米ニューヨークのマネス音楽院修了。メトロポリタン歌劇場の「魔笛」夜の女王で大成功を収めた。オーストリアのリンツ州立劇場の専属歌手を務め、欧米の多数の歌劇場で活躍。近年ではザクセン州立歌劇場で「蝶々夫人」を主演。国内では、兵庫県立芸術文化センター、日生劇場、新国立劇場、びわ湖ホールなどの歌劇場にて、バロックからベルカント、ヴェルディ、プッチーニ、シュトラウス、ワーグナーの作品まで多種多様な役柄を演じ、常に高く評価されている。近年ではプーランク「人間の声」が新聞各紙で高評され、「ルサルカ」「真珠とり」「トスカ」の主演でも聴衆を魅了した。オーケストラとの共演では、ベルク「ヴォツェックより3つの断章」、R.シュトラウス「4つの最後の歌」などが絶賛され、ドイツではARDジルベスターコンサート及びゲヴァントハウスでMDR交響楽団とフィリップ・グラス「The Voyage」はドイツ国内に放送され、鮮やかで高度な歌唱を印象付けた。リサイタルでは「Spirit of Language-言霊-」シリーズを展開中。小山評定ふるさと大使。とちぎ未来大使。下総皖一音楽賞受賞。
東愛知新聞にて新連載が始まりました
東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての連載⑤

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。
【連載】三河市民オペラの冒険〈5〉
三河市民オペラはどうすごいのか
(音楽評論家・河野典子)
三河市民オペラ(以下、「三河」)は数ある市民オペラでも特殊な存在で、それは「制作委員会」の働きに帰するところが大きい。
制作委員会のメンバーが地元企業経営者らに頭を下げて回って公演の資金をかき集め、チケットを売り、マイカーを出して出演者や関係者の送迎運転手もこなし、当日は「携帯電話のスイッチをお切りください」というプラカードを持って客席をくまなく歩き、公演中に高級ホテルのドアマンよろしく、扉の前に立ったまま舞台を見守る彼らの姿には、ワーグナーのオペラ「タンホイザー」の巡礼の合唱が聴こえくるような崇高さすら感じるのだ。普段オペラとは縁のない人たちがそれらを手弁当で務めているのである。「熱い感動を生み出す」というつかみどころも捉えどころもないようなことを目標として、いい歳をした(失礼)大人たちが一丸となっているところこそが「三河」が他の市民オペラと違う点だ。
新国立劇場をはじめとした公立の劇場、年に数回のオペラ公演を打ち続けることが求められる、いわゆるプロのオペラ団体は、毎月のように次の作品のキャスティング、準備、稽古そして公演を繰り返す。「三河」は数年に一度だからこそ、これだけのことができるのであって、そこを同列に語ることはできない。だが、東京や関西圏を中心に活躍する歌手たちが、こぞって「三河」の公演オーディションに、新幹線代を払ってまで集まってくるというのは、他の市民オペラではまず見られない現象である。出演者たちを触発するのは、制作委員会メンバーが醸し出す「やる気」と「本気」である。
成功を重ねれば重ねるほど、そこに期待と責任が生まれてくる。事前に出演を依頼する指揮者、演出家、数名の歌手たち以外については、公明正大なオーディションを行わねばならない。地元の合唱団やオーケストラ、舞台のみならず手を貸してくださる数多のスタッフの方々とも熱意を共有して活動しつづけること、国内外の他団体からノウハウを聞かれれば、それをつまびらかにしていくこともこれからもっと求められるだろう。それが、衰退しつつあることを否めない「日本におけるオペラの存続」に直結しているのが今の「三河」の立ち位置である。
「三河」はこれまで「魔笛」「カルメン」「トゥーランドット」「イル・トロヴァトーレ」「アンドレア・シェニエ」と公演を重ねてきたが、オペラというもののも魅力を地元のお客さまに知っていただき楽しんでいただくためという目的のもと、日本人歌手が歌うには重すぎるレパートリーに向かって舵を切ってきた。集客力という点で、大きなオペラ作品を採り上げることは大事な要素ではある。だが、重いものばかりが素晴らしいオペラというわけではない。歌舞伎でも「勧進帳」や「暫」のような様式美の時代物もあれば「髪結新三」や「廓文章」などの世話物があるように、どちらかがお好きな方もあれば、同じ役者さんがどう演じ分けられるかを楽しみに劇場にいらっしゃるお客さまもある。「風の谷のナウシカ」のような新作物に若い観客が押し寄せることもある。
オペラ関係者と「お客様をなめるな」と話すことがあるのだが、「難しいものはわからないだろう」「有名なものを掛けていれば安全だろう」という発想はとんだ筋違いだということを「三河」は「アンドレア・シェニエ」で証明して見せた。いわば通好みの「シェニエ」で普段オペラをご覧にならないお客さまを感動の渦に巻き込んだのである。
さてここからの「三河」が、演奏家の「一度は手掛けてみたい」という身勝手な都合に振り回されるのではなく、どんな自分たちの基準を持って、どこに向かっていこうとするのか。私はそれをとても楽しみに見ている。
◇
東京藝術大学卒業後7年間在伊。帰国後、執筆活動、歌手のサポート、録音プロデューサー、文化庁の審査員などを務める。著書に「イタリア・オペラ・ガイド」。
三河市民オペラ 2023年公演
最新情報
Latest information
三河市民オペラ合唱団員・サポーター 募集のお知らせ
制作委員会(WEB管理)2021-09-15T19:13:13+09:002021年9月15日|
三河市民オペラ
2023年公演 上演決定!
制作委員会(WEB管理)2024-05-02T23:48:16+09:002021年9月1日|