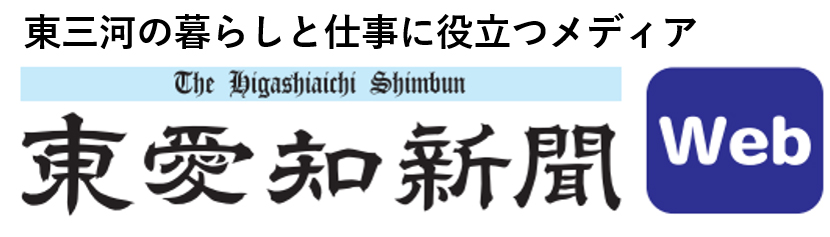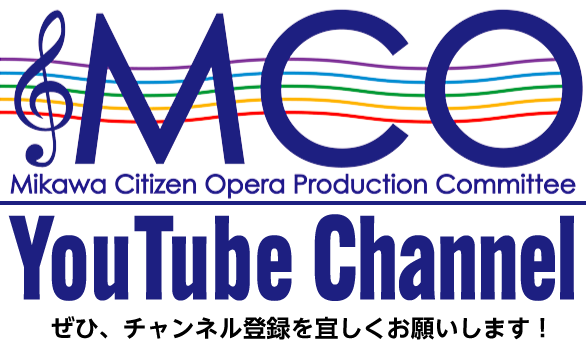Headline News
東愛知新聞にて新連載が始まりました
東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての連載③

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。
【連載】三河市民オペラの冒険<3>
「また観たい」伝わった熱量
(オペラ評論家・香原斗志)
(写真・右から)聴くたびに進化するメッゾソプラノの脇園彩さん、筆者、大輪の花を咲かせると期待されるテノールのステファン・ポップさん=イタリア・ボローニャ歌劇場の楽屋で
制作サイドの熱量が高いオペラは客席も沸く。最たるものが、2023年5月に上演された三河市民オペラのジョルダーノ作曲「アンドレア・シェニエ」だった。私は打上げであいさつした際、「ミラノ・スカラ座の公演よりも盛り上がった」と話したが誇張ではない。オペラの殿堂と芸術的な水準を比較しているのではない。客席の熱気は、たしかに豊橋が上回っていた。
もちろん、指揮者、演出家、歌手、合唱、オーケストラという「素材」は重要だが、それらが一定の水準でそろったあとは、客席の反応、すなわち観客の心の動かされ方が、舞台から伝わる熱量に左右されるのは間違いない。
私はオペラ鑑賞が生活の一部である。昨年は欧州だけでも30公演程度は鑑賞したが、本場のすぐれた公演でさえ心を打たれるとは限らない。ましてや国内の公演は、客席にいることを後悔することも珍しくはない。しかし、そんな中で心が躍った公演には共通して熱量があった。
昨年12月、藤沢市民オペラのモーツァルト「魔笛」は、温かくまとまった質の高い公演だった。同じ月には、神戸文化文化ホールがオペラの制作にはじめて挑んだヴェルディ「ファルスタッフ」を鑑賞したが、総力を挙げた熱気が客席を包み込んだ。ちなみに両公演とも満席だったが、それは上演前から熱気が伝わったからだと思う。
したがって三河市民オペラも、周囲を引っ張る制作委員長の高い熱量が失われないかぎり、ふたたび成功することを少しも疑わない。
■みな正のエネルギーを欲している
「人はパンのみにて生くるものにあらず」。だが、この失われた30年においては、パン以外のものに触れて人生の養分を吸収する余裕を、私たちの多くが失っているように見える。だから、SNS上での憂さ晴らしが後を絶たず、人々の心から潤いがさらに失われていく。
そんな状況だからこそいっそう、私たちは熱いものに敏感になっているように思う。
残念ながら熱量が低い公演は、オペラの裾野の拡大につながらない。一方、三河市民オペラの「アンドレア・シェニエ」のほか、前述の「魔笛」や「ファルスタッフ」は、初めてオペラに足を運んだという人の多くが「また観たい」という感想を残している。それは芸術としての質もさることながら、私たちが早く脱したいと願ってやまない失われた30年とは別の方向を向いた、正のエネルギーが漲っているのを感じるからではないだろうか。
とりわけ三河市民オペラは、資金集めから制作業務まで地域経済を担うビジネスマンたちが携わって、その行動力や人脈を生かしている。多額の協賛金を集め、チケットはすべて売り切る。そうした力はおそらく出演者のほかあらゆるスタッフに伝わり、観客に向けた熱として発散されるのだろう。
■熱量さえ失わなければ
たしかに「アンドレア・シェニエ」は出演者が多く大がかりで、上演が困難なオペラの一つである。知名度も高いとはいえない。それを圧倒的な成功に導いたあとで再度、観る人の胸の内を熱くすることができるかどうか、不安になるのはわかる。諸物価が高騰し、以前の制作費では賄えないのも事実である。
だが、もっとコンパクトに上演できて、日本に適任の歌手がいて、これまで以上の感動を呼び起こすポテンシャルがあるオペラはたくさんある。そこにこれまでと同じ熱量を注ぎ込んでいただけるなら、私たちはパン以外の大事なものを吸収し、それを未来への希望につなげることができる。失ってはいけないのはただ一つ、熱量である。
※神奈川県生まれ。早稲田大学卒業、声楽作品を中心にクラシック音楽全般について執筆。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「歌声のカタログ 魅惑のオペラ歌手50」(共にアルテスパブリッシング)など。毎日クラシックナビ「イタリア・オペラ名歌手カタログ」などの連載をもつ。歴史評論家の顔もあり、近著に「教養としての日本の城」(平凡社新書)「お城の値打ち」(新潮新書)。
東愛知新聞にて新連載が始まりました
東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての連載②

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。
【連載】三河市民オペラの冒険〈2〉
とてつもなく熱い「何か」
(NHK名古屋放送局・吉田英司)
私が初めて三河市民オペラの稽古場を訪れたのは、公演の2カ月前、2023年3月のことだった。まだ番組の企画書は白紙。どのような切り口で取材できるか、手探りのスタートだった。
合唱稽古を見学し「三河市民オペラ制作委員会」のメンバー数人に話を聞いた。委員会を構成する24人は、地元豊橋で会社を経営しながら、オペラ制作の裏方を支えていた。稽古場の確保から出演者のケア、数千万円におよぶ資金調達まで、膨大な役割を無償でこなしていた。
本業と私生活の時間を削り、彼らはなぜこれほどまでに献身できるのか。その答えを求め、私は彼らの言葉の奥を探った。しかし、核心に迫る言葉は容易には見つからない。企画書を書けないまま、見切り発車のような形でデジカメを片手に豊橋に通い始めた。
最初に密着取材したのは、協賛金を集める場面だった。24人の制作委員が手分けして約400社の地元企業を回り、1口2万円からの出資協力を呼びかけていた。年度末の多忙な時期に、まだ見ぬオペラの魅力を懸命に説いて回る姿を見ていて、少しずつわかってきた。彼らを駆り立てていたのは「この先に、とてつもなく熱い『何か』が生まれる」という確信だったのだ。
その確信の源は、制作委員会のリーダー鈴木伊能勢さんの「舞台と観客が一体となった本物の感動を生み出す」という揺るぎない信念にあった。彼は圧倒的な熱量で周囲を巻き込み、有無を言わせぬ引力で制作委員のメンバーを導いていた。
さらに、豊橋という土地に根付く経済人たちの強固な結束も、このオペラを支える大きな力となっていた。青年会議所の若き経営者たちは持ち前の行動力で精力的に走り回り、彼らを支える先輩世代は、長年培った経験と人脈を生かして役割を果たしていた。
彼らの献身は、23年5月に上演を迎えた歌劇「アンドレア・シェニエ」で実を結んだ。一流のオペラ歌手と舞台スタッフ、地元のオーケストラと合唱団、裏方で奔走した制作委員、協賛した地元企業、そして客席を埋め尽くした2日間延べ2700人の観客…。すべてが一体となった会場の高揚感に私は震えた。圧倒的なクライマックスで幕切れを迎えた瞬間、会場はスタンディングオベーションの熱狂に包まれた。「とてつもなく熱い『何か』」「舞台と観客が一体となった本物の感動」が、確かに生まれたのだ。
しかし、この成功を目の当たりにした私は、同時にある種の難しさも感じた。これは、どこでも再現可能な成功モデルではない。情熱の塊のようなリーダー、組織立って動ける強固な地域コミュニティー、そして無償で奔走する約20人の精鋭たち。これら全ての要素がそろう場所が、他にどれほどあるだろうか。
三河市民オペラが、あの感動を今後も生み出し続けていくのは容易なことではないだろう。しかし、だからこそ、彼らには「感動のため」という原点を守り抜いてもらいたい。制作委員の一人が、ドア係を務めながら初めてオペラの舞台を目にし、人目もはばからず号泣していた姿を、私は忘れられない。あの感動の現場に立ち会えた時、彼らはきっとこう思ったはずだ。「すべては、この瞬間のためにあったのだ」と。
◇
神戸市出身。1999年入局。初任地の大分で地域放送に携わった後、東京でクラシック音楽の番組を15年間担当。その後、大阪勤務を経て名古屋に異動。地元の音楽文化を取材してきた。23年5月に三河市民オペラを取り上げ、ニュース番組「まるっと!」でリポートを、情報番組「さらさらサラダ」で特集企画を放送した。